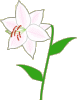|
(1)
化学工場の作業現場で背中に火傷をした時の痛みが夢に現れて、ハッと目が覚めた。苛性ソーダが頭上のパイプの一部から漏れて降り注いでおり、それをヘルメットで避けてはいたが、背中にも降りかかって徐々に滲みていたのだった。作業服を溶かして、背中が熱いと気が付いた時には、すでに手遅れだった。背中はみるみる爛れていたらしくて、喚き叫びながら、その日、すぐに救急車で搬送されたのだった。後になって祐一郎は、本当にオレは何をやっても役に立たない男だなと、しみじみと思ったものだった。危険な作業現場ではいつも先輩に呶鳴られっぱなしだった。
火傷の痕は残ってしまったが、自分でわざわざ背中を鏡に映して見ることもないので、あの時の作業事故を思い出さなければ、とっくに過去のことで今はすっかり忘れてしまっている。生涯でたった一人、梨沙だけが祐一郎の醜い背中に触れて「かわいそうに、こんなになってしまって」と慰めてくれたのだった。裸の姿で後ろから彼の肩に両手をかけて、凭れながらうなだれて、ささやいていた。祐一郎は自分の肩に手を置いた梨沙の左手を、そっと握り締めた。梨沙の体温があたたかかった。
そんな優しい梨沙も、今はそばにいない。眠りから覚めた祐一郎は、カーテンの開いた自宅アパートの窓の外を見つめた。外は霙のようなものが降っていた。春になったら、梨沙の墓参りに行こうと思っていたが、自分ももうすぐ梨沙のもとへゆける気もしていた。外が晴れたら、もう一度京都を歩いてみたいと思った。梨沙には祇園祭も葵祭も見せてやれなかったけれども、いろんな所を歩いた思い出だけはいっぱい残っていた。
数日後、交通費と多少の小遣いを得るために、祐一郎は地下鉄で梅田まで古本屋に本を売りに行った。阪急古書街で、手提げ袋に入れて来た啄木全集と哲学書を何冊か売って、お金に換えた。手放す本はいつも未練のない書物ばかりだった。感銘を受けたり尊敬している作家や学者の書物だけは、なぜかどうしても手放せなかった。梨沙の父君こと辰野先生から譲り受けた中国古典文学大系も、何度かこっそりとお金に換えようと誘惑にかられたけれども、結局、今も手元に残っていた。ずるくて経済力に乏しい己れの半生が恨めしいような、その一方でいつまでも甲斐性のない自分を追い詰めるほどには覇気もなく、ただダラダラと惰性と夢想でしか生きられなくなっている自分をまた、どうすることも出来なかった。
祐一郎はそのまま梅田から地下鉄御堂筋線で乗り継ぎ淀屋橋から京阪電車で京都まで行った。大阪は晴れていたのに、四条京阪で降りると、京都は小雪がちらついていた。南座の前から円山公園の方を眺めると、八坂神社がうっすらと雪化粧をしていた。祇園の方へは行かずに、自然と足が鴨川の方へ向いた。四条大橋の真ん中あたりまで来ると、北山がすっぽりと雪の雲に包まれて見えた。比叡はすでに真っ白だった。鴨川の上はずいぶん冷たい風も吹きつけて、街中も今にも大雪になりそうな気配である。祐一郎はとても寒かったが、京都の冬は本当に美しいと思った。三条大橋に現れる擬宝珠の下の乞食は、こんな寒い雪の日でも菓子の缶を置いて物乞いしているのだろうかと興味も湧いた。頬被りをして下を向いているので顔はよく見えないが、もしこんな雪の日でも路上で物乞いをしていたら、きっと大した奴だと尊敬したくなった。いつも半袖の破れた肌着だったが、冬はそうはゆかないのではないかと、ますます確かめたくなって、橋を渡ると先斗町の狭い通りを四条から三条へと彼は歩いていった。
三条大橋の袂までやって来たら、乞食はやはりいつもの格好で物乞いをしていた。祐一郎はもしかしてこの乞食は修業僧ではないかと思った。しかし、京都で修業している僧侶たちはきちっと托鉢をしており、路上に胡座をかいて、ここまでこんなことをするとはとても信じ難かった。乞食の前で祐一郎は立ち止まった。1円玉と5円玉と10円玉がパラパラとしか缶の中には見えなかった。たぶん紙幣が投げ込まれたら、先にそれだけをポケットにしまうのだろう。祐一郎は思い切って、しゃがみ込んで乞食に声をかけてみた。
「寒いんじゃないの?」と話しかけてみた。すると、
「あ、あっちへ行け」と怯えながら乞食は顔を上げずに喋った。
祐一郎は意外な返答に「えっ」と言って、あらためて乞食をまじまじと見詰めた。そして、頬被りをして俯いている乞食の顔をそろりと覗くと、薄汚い老いた醜い祐一郎の顔がそこにあった。祐一郎はギョッとなって、後ろへ尻餅をついてしまった。
「お前は誰だ?」と祐一郎が叫ぶように訊くと、
「お前さんだよ」と乞食は嗄れた声で言ってから、顔をゆっくりと上げて祐一郎をニヤリと見据えた。
そして、「ああっ!!」と夢の中で叫ぶと同時に、祐一郎はやっと目が覚めた。ひどい寝汗をかいていた。
その日、確かに梅田に古本を売りには行ったが、けっきょく京都には行かなかったのだった。まっすぐ阿倍野の自宅のアパートに帰り、疲れていたのでそのまま床に就いたのだった。昼も夜も寝床に就く日が多くなっていた。幻覚なのか夢なのか、この頃の日常生活に境目がない暮らしを続けていた彼ではあった。堕落と幻覚がますます病気を重くしていた。春になって梨沙の墓参りだけには行こうと、そのことだけは脳裡から消えなかったのである。暖かい春が来るには、まだいくらか遠い2月半ばの梅の季節ではあった。
(2002/01/28)
(2)
再び新緑の京都を訪ねたのは、梨沙と一緒に訪ねた、ちょうど1年前の5月の今頃だった。梨沙の墓は大阪だが、思い出は京都にあった。祐一郎は墓参りを済ませた翌日、また梅田の阪急古書街に行って何冊かの本を売った。梅田からは阪急電車で四条河原町まで行った。そこからバスで出町柳まで行き、京福電鉄(いま叡山電鉄)で鞍馬へと向かった。
貴船の椿楼で天の川を一緒に見つめた日の一夜が思い出された。本当に、はかない、つかの間の思い出になってしまった。その2ヶ月後に梨沙は体調が急変してしまったのである。ひどい衰弱の仕方で、病名は膵臓癌の末期ということだった。当時、娘を亡くした辰野家では、柏木祐一郎は門前払いを受けていたが、葬儀が終ってから初七日に、梨沙の父君である辰野肇教授が一人で阿倍野の柏木の狭いアパートを訪ねて来た時には、祐一郎もびっくりした。
「柏木君。私はね、ごく普通の父親として、ここへやって来たよ」と言われた。
「‥‥‥ 」祐一郎は言葉を失って何もしゃべれなかった。
「家内は今も君のことを許していないがね、どこに悲しみをぶつけていいのか判らないから、ずいぶん残酷に君を罵ったかとは思うが、この通り、許してくれたまえ」と祐一郎の前で正座した辰野教授は、頭を深々と下げて肩もガックリと落とした。
「先生、やめて下さい。僕が何もかもを滅茶苦茶にしたから悪いんです。謝らなければならないのは、この僕の方なんです」
と祐一郎は悔悟の念で泣きながら自分も頭を垂れた。
そして、しばらくしてから、
「柏木君。実は後でこれが見つかってね。娘の精一杯の遺書だったよ」
と辰野教授は背広の内ポケットから白い封筒を取り出した。
「私と家内へ宛てた娘の遺書だよ」
祐一郎は動揺しながら言った。
「先生。よろしかったら、何が書いてあったのか教えて下さい」
「君に見せたいと思ってね、それで今日ここをやっと探してね、実は来たんだ」
「そ、そうだったんですか」
祐一郎は手渡されるままに、その遺書を恐る恐る震える手で開いていった。
便箋一枚の簡素な遺書であった。病院内で書いたのだろう。ボールペンで弱々しく、けれども見事な達筆であった。
「お父様 お母様へ この病気と闘って、もう5年余りが過ぎてしまいました。本当にいろいろとありがとうございました。看病疲れのお母様、本当にわたくしはあなたの娘として幸せでした。短い命でしたけれども、これも運命ですもの。わたくしの尊敬する大好きなお父様を、終生支えていってあげてくださいね。娘はもう力がすっかり萎えてしまいました。先立つ親不孝を、どうぞ御許しくださいね。この病気が癌であることは、うすうす知っています。たぶん、もうあとひと月も持たないでしょう。こうして文字が書けるのも、これできっと最後でしょう。
お父様に最後のお願いがあります。もう一度、柏木さんにお会いになって頂きたいの。娘の代わりに、伝えて頂きたいの。わたくしは生きているうちに、もう二度と柏木さんに会えませんけれども、天の川でいつも祐一郎さんを見守っています、って伝えて頂きたいの。わたくしの人生のすべてを祐一郎さんに捧げます。お父様、お母様、どうか、お体に気を付けて、あなた方の娘梨沙の分まで、ずっとずっと長生きしてくださいね。本当にありがとうございました。 梨沙」
柏木祐一郎は読み終えて、体中がぶるぶる震えていた。
「すまなかった。どうか、私達を許してくれたまえ」と辰野教授は大粒の涙で頭を下げたままだった。
祐一郎は思わず気が狂いそうになった。強引にでも梨沙が生きているうちに一目会うべきだったのだ。どんなにか梨沙が絶望的な悲しみで息を引き取っていったことか、そう思うと何ともやりきれなかった。だが、頭を下げている一人の父親の姿に、一方で憎しみを覚えながらも、祐一郎はむしろ娘の父親としての最後の威厳のようなものを感じた。娘の遺志を伝えに来た辰野教授の姿は、ごく普通の父親の姿として立派に思えた。
「先生。わざわざ今日はありがとうございました。こんなむさくるしい所へ来て下さり、まだお茶も出さないで」
「いや、柏木君。何もお構いなく、君には何もしてやれなかったが、しばらくそれを君に預かって欲しいんだが」
と辰野教授は梨沙の遺書を指して言った。
「でも、これは、大切なお嬢さんの」
「いや、妻と相談した結果、娘の供養になるには、これをせめて最後の娘の形見として、大事にしてくれる君に預かってもらいたいと思ったんだよ。娘は自分の人生のすべてを、柏木君に捧げたのだからね。今更と思うかもしれないが、本当に君にはすまないことをした」
「先生、もういいんです」
「君と会わせてやってれば、もう少し長く生きてたんじゃないかって、悔やんでも悔やみきれないよ」
「梨沙さんはとっても親孝行な方でしたから、そんなふうには考えていなかったと思います。これは遺書というより、心のこもった御両親様への手紙ですよ。むしろ、お嬢さんの人生のすべてを捧げるだけの価値が、この僕にあるのでしょうか?」
「娘は私達親から言うのも変だがね、いくら世間知らずだったとはいえ、人を信じる眼だけはとてもきれいだったよ」
「そうですね。反対に僕の眼は、世間を見る眼が、汚れていたかもしれません。お嬢さんの眼はとても美しい眼でした」
柏木は梨沙の遺書を両手で持って、辰野教授に「預からせて頂きます」と言った。
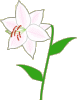
あれから10ヶ月が過ぎた新緑の5月の京都にやっと来られた自分が、祐一郎は夢のように嬉しかった。いや、今度こそ夢であってはならなかった。貴船の椿楼に、去年梨沙と約束したように、二人で天の川を見に来なければならなかったのである。祐一郎は梨沙の遺影と遺書をバッグに入れて電車に乗っていた。その日、椿楼には柏木祐一郎の名前で二人分の宿泊の予約をしていた。
貴船口駅で降りると、宿まではタクシーで行った。懐かしい渓流の音がしていた。去年とまったく変わらない山間の風景だった。
「お越しやす」と出迎えてくれたのは、去年お世話になった同じ女将の姿だった。
「お連れのお方は?」
「二人分の予約で用意して頂けますか? 梨沙も一緒です」と柏木が言うと、
「へえ。ご用意させて頂きます。梨沙さんはもうすっかりお元気どすか? 去年はずいぶんお痩せになってはりましてたけど」
「憶えていらっしゃったんですか?」
「そらよう憶えてます。あんときは大変やったさかいになあ、心配しましたんどっせ」
「実は、あれから大阪で入院することになりまして、2ヶ月後の七夕の日に、癌で亡くなりました」
「ええっ、そら知りまへんで、すんまへん、堪忍え。まあ、そうだしたんどすか。えらいことになったんどすなあ」
と女将は茫然と立ち尽くしていたが、すぐに、
「珠子はん、バッグお持ちして。慎之介はん、お部屋の方へすぐご案内してや。さァ、どうぞどうぞ、ゆっくりおくつろぎくださいね。ほんまになあ、お気の毒なことになりはったんどすなあ」と女将は言いながら、しんみりと目頭を押さえていた。
その夜、祐一郎は部屋の窓際のテーブルに小さな額の梨沙の遺影を立てて、夜空を眺めた。あいにくと曇っていて、あまり星は見えなかった。けれども、彼には天の川を眺めた去年のことが想い起こされていた。「また二人で一緒に来ましょうね」と誓い合った約束を果たしたことで、祐一郎は心安らかな気持ちで幸せを感じていた。
「これでもう決して離れ離れになることはないからね」
と祐一郎はぽつりとつぶやいた。部屋には二人分の食事が用意されていたが、箸はまだ付けていなかった。
「もうすぐ僕もそちらに行くからね。二人で天の川を渡ろうね」
と囁きながら、再び祐一郎は窓から顔を出し、夜空を見上げた。雲と雲の間から、わずかに星々がまたたいているだけだった。いつまで待っても薄曇がかかって夜空を流れていた。
「きみの御両親がね、僕たちのことを許してくれたよ」と祐一郎は、遺影の額と一緒に並べた梨沙の遺書に、手を触れてささやいた。
「僕の残り少ない人生も、すべてきみに捧げます」
長い静かな供養の夜だった。祐一郎は二人分の食事をゆっくりと平らげた。食べ終わると、それらを下げてもらい、寝床の用意をしてもらった。やがて気がつくと、今にも夜が明けそうな時刻になっていた。外は真っ暗だったが、窓を開けてみると、願いが叶ったのか、満天の星々が夜空にこの上もないような美しさで無数の光をちりばめていた。雲がまったくかかっていなかった。月の光もなかった。こんなにも星があるのだろうかと、あらためて彼は驚いた。どこからともなく「天の川ね」と、梨沙の声が聞えた。深い夜の闇に浮かびあがった天の川の明滅と、澄みきった梨沙の声に、祐一郎は安堵し、窓を閉めて、やっと床に就いた。そして間もなく、夜はしらじらとすぐに明けていった。
梅雨が明けやらぬ2ヶ月後の7月7日七夕の頃に、柏木祐一郎は数日食事も摂らずに、静かに阿倍野の自宅アパートで心不全で亡くなっていた。妹の千鶴と夫の信彦が警察からの兄の訃報を聞かされて、新潟の高田から大阪の阿倍野の兄祐一郎のアパートを訪ねて来たのは、7月10日であった。部屋にはこれといった家財道具もなく、衣類も質素で、部屋には生活の暮らしらしいようなものは何もなかった。書籍がわずかばかり残っていただけだった。この時、千鶴には兄がそれまでどんな生き方をしていたのかは、もちろんまだ何も判らなかった。書籍類の内、伊東静雄の詩集に梨沙の遺書が本に挟まっていることは、まだ何も知る由はなかったのである。
(完)
(2002/07/22)
平成14年7月22日 脱稿
|